| 四十代天武天皇 四十五代聖武天皇 |
難波長柄豊碕宮は御三十六代孝徳天皇難波 遷都の皇城で、天皇こゝに都を遷し給ふや中 大兄皇子を皇太子とし中臣鎌足を用ひ、はじ めて年号を立てゝ大化と稱し所謂大化改新が 行はれたところで、國史上重要な意義を有す るものであり、殊に大阪市民としては仁徳天 皇の難波高津宮とともに、忘れることの出来 ないところで、天武天皇の御代に一度修覆さ れまた聖武天皇の御代には大修理が施され、 以後百五十年間「難波宮」として存續したこと | 24丁表 |
|
は正史に明かであるが、千年といふ長い時の 推移に遂に跡形もなくなって了ったのである 。 古来この宮跡に就ては史學者間に三つの説が ある。 それは現在の豊崎神社附近から長柄へかけて の一帯の地がそれだといふのと、埀水の庄か ら水を引いたといふので新淀川の右岸、東宮 原、南宮原、北宮原と稱ふる宮原の地一帯が 宮跡であらうと説かれてゐるのと、長柄本庄 方面は卑濕な水郷であって皇居に適せず、豊 崎は即ち岬で高爽な地勢であるから、渡辺の 堀江の上なる大阪城の高台の邊だと云ふ説で | 24丁裏 | |
| 十五代應神天皇 |
ある。 これらとて何れも宮跡に就ての確たる史実文 献があって云ふのでない。 今の長柄本庄の地だといふ史学者は地名のみ に拘泥せず、地勢を考證して孝徳天皇の奠都 より三百五十餘年以前には應神天皇は大隈宮 を營み給ひ、又是れより凡八十年以後である 聖武天皇御宇に於て、僧行基は源光寺や、我 國三昧火坑の嚆矢である濱の墓所を創建した 、或ひは近くに國分寺の旧蹟がある。 また鶯塚などみなこの附近であって近くは明 磁二十九年新淀川開鑿工事の時、長柄辺の土 中より種々の彌生式土器を発掘した事がある中に、 | 25丁表 |
| 六十六代一條天皇 |
酒壷の完全なもの数個現はれ何れも千年以上の ものだと云はれ、この長柄本庄説を裏書する ものであると主張してゐる。 一條天皇の正歴年間(今より九百三十餘年前)に創 建したと云はれる豊崎神社の縁起にあるやう に、故宮の湮滅することを畏れて創祀したと いふ事も考へられる。 しかし惜しい事には明和九年に豊崎神社が炎 上して孝徳天皇の御衣と傳へる、上古の金襴 一片を残すのみとなって古文書をすっかり焼 失してしまった。 昭和八年二月大阪史蹟調査會と趣味の考古学 會によって、長柄本庄豊崎方面一帯に亘って | 25丁裏 |
|
調査した事があったが、何等得るところが なかったといふ。 「大阪府誌」はこの長柄本庄説を採って今の豊 崎神社附近一帯であらうと書いてゐる。 それによると豊碕宮は廣大なる地域で、支那 の長安京に模せられた都城で威儀整然犯すべ からざる禁苑であった事が判る | 26丁表 | |
|
然るに最近になって豊崎神社から数町はなれた 東洋紡績大阪工場の庭内噴水工事の際圖らずも 発掘された家型埴輪は珍らしいもので、惜しいことに 三片に破損してゐるが、これを繋ぎ合すと完全な ものになる。これによって我舊史時代の建築物を 見ることが出来る。屋根には千木や堅緒木の 状態がよくわかり、今から凡そ千三百年以上経て ゐるという時代考證も確実なものでいよ〃〃 長柄豊碕宮の皇居の跡を立證するもので 長柄本庄説が、極めて有力となってきた。 | 挿入一紙 (四月十七日 火曜日日めくり) | |
|
豊崎神社社司友田氏の語るところによると右発掘され るや心なき土工のためにあはや、只の瓦礫として粉砕される ところを乞うて神社に寄附を受けて大切に保管さ れてゐる。近日其筋の史学者に鑑定を依頼して、この 貴重な資料発見によって、從来の異説を覆 へす日も近いであろうと期待される。 | 挿入一紙裏 | |
|
日本書紀 孝徳天皇紀 大化元年冬十二月乙未朔癸卯、天皇 遷都難波長柄豊碕、老人等相謂之曰、 自春至夏鼠向難波、遷都之兆也 | 26丁表(続き) | |
|
同天皇紀 大化四年春正月壬午朔賀正焉是夕 天皇幸于難波碕宮 白雉二年冬十月晦於味経宮請二千一 百餘僧尼使讀一切経(中畧)於是 天皇從於大郡遷居新宮、号曰難波長 柄豊碕宮。 白雉三年春正月已未朔元日禮訖、車 駕幸大郡宮(大郡は即ち東成郡にして宮 は味経宮也) 三月戊午朔丙寅、車駕遷宮。 同五年冬十月癸卯朔、皇太子聞天皇 病疾乃奉皇祖母尊間人皇后拜率皇弟 | 26丁裏 | |
|
公卿等赴難波宮。 壬子天皇崩于正寢。仍起殯於南庭。 齊明天皇紀 元年秋七月已巳朔已卯於難波朝饗北 北越蝦夷九十九人東東陸夷九十五人拜 設百濟調使一百五十人。仍授棚養蝦 夷九人、津刈蝦夷六人冠各二階。 六年十二月丁卯朔庚寅天皇幸難波 宮。 夫木集 いにしへの長柄の宮は跡もなし | 27丁表 | |
|
橋柱だに朽果つる代に 公朝 御集 橋柱ふりぬる影の浪にはれて 長柄の宮の月のみぞすむ 後柏原院 | 27丁裏 | |
|
豊崎神社 豊碕東通四丁目に鎭座。 孝徳天皇を主神として相殿に須佐男命を祀る 。 由緒に依ると長柄豊碕宮の旧蹟地で宮の廃せ られし後、星霜を経るに從ひ荒蕪の地となり 、宮跡の一隅は一帯の松林となって世人はこ れを八本松と呼んでゐたのを、正歴年間藤原 重治、これを開墾するに當り、孝徳天皇故宮 の湮滅せんことを畏れ樹林中に小祠を建立し て、皇蹟を崇敬追拜し奉ったのに起る。 | 28丁表 | |
| 明和九年 百十七代後櫻町天皇 徳川時代 百七十二年以前 慶長十九年− 百八代後水尾天皇 織田、豊臣時代 三百三十年以前 |
後村民の望に依って須佐男命を合祀したが惜 しいことには、明和九年六月二十九日社頭炎 上に及んで神輿の帷帳と上古の金襴一片を残 すのみで旧記等悉く焼失した。 明治五年村社に列せられ、明治四十一年四月 七日大字南長柄の村社八幡神社を本殿に合祀 し、又近くにあった無格者東照宮社(徳川家康) を境内に合併し、更に同嚴島神社(市杵島姫命) を同東照宮社に合祀した。 東照宮社は慶長十九年大阪冬の陣のとき徳川 家康微傷を帯び、同村足立市兵衛の宅へ立寄 りたる際、市兵衛より差出せる麥飯を食べ頗 る満足その姓を尋ね足立であると答へたによ | 28丁裏 |
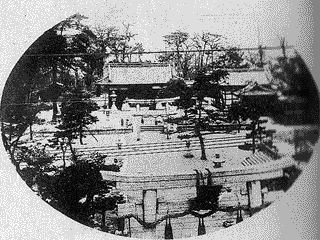
豊崎神社 | ||
| 安永五年− 百十八代後桃園天皇 徳川時代 百六十八年以前 寛永 百九代明正天皇 徳川時代 三百十餘年以前 |
り、家康大に喜び永く足立と唱へよとて紋 章等を賜った因みにより、安永五年三月旧領 主田安家へ出願許可を得て足立家邸宅内へ鎭 守として崇奉祭祀したものだといふ。 境内は二千五百四十一坪を有し、本殿、幣殿 、拜殿、神輿庫、神具庫、社務所等相連り、 末社に豊受皇太神宮、恵美須神社、鹿島神社 がある。 鹿島神社の祭神は武甕槌命で寛永の初め、諸 國に疫病流行したので常陸國から勧請し、神 輿を渡して平寧を祈ったといふ。 當時鹿島踊が盛んであったが今はない。 攝津名所圖會にいふ。 | 29丁表 |
|
神島神祠 本庄村にあり祭神武甕槌命、今天皇と稱 す、寛永の初め、諸國疫病流行し常陸の 鹿島神を勧請し、神輿をこゝにわたす、 又村中をどりを催す、これを鹿島踊とい ふ、此地の産土神とす。 豊崎神社は昭和五年より社殿其他改築造營に 着手して、十ヶ年の歳月を要し昭和十五年竣 功して現在のやうになった。 | 29丁裏 |