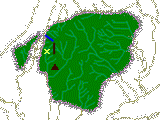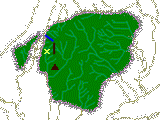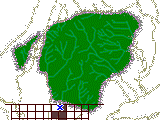←前|↑表紙|→次
桜井谷の入会山 附・東寺領垂水荘
古文書に現れる「千里山」 |
千里丘陵に関係する地名として「千里山」なり「千里」が最初に登場するのは、知り得る限りでは、慶長年間の入会山論に関する片桐且元らの文書2通だ。これらの文書では「摂州豊嶋郡之内千里山」の範囲を明示的には述べていないが、訴えの当事者として、熊野田村と桜井村がセットで登場するので、この両村の間の丘陵地を主たる対象にしていると考えてよい。ここは、前章で見た、豊島郡誌・大阪府地誌系の「千里山」の中心部でもある。また、争論の相手方に小曽根村のような熊野田のずっと南の村が登場していることから、熊野田南方の丘陵(現服部緑地のあたり)も含まれているかも知れない。一方、北方・西方の村は、この争論には登場しないので、待兼山の並びは意識されていないのではないだろうか。
この一帯は、仏念寺山断層の真上に当たる。断層の東側(千里丘陵本体隆起)は天竺川に向けて比較的緩やかに下り、西側(東側に引きずられるように上がった部分)は、桜井谷(千里川河岸)に向けて急傾斜を見せる。その中央部には、概ね南西に向けて下る浸食谷が多数あり、次々に合流して兎川となって南行し、熊野田の南西で天竺川に合流している。桜井谷側には、西に下る短い谷が多数並んで千里川に向かう。天竺川の水系に属する谷とその周辺は、概ね熊野田村が権利を主張していたが、その北部、竹谷と呼ばれる一帯をめぐっては、桜井村との境争論が発生する。ともあれ、上記の文書の時点では、両村は共同戦線を張って、豊島郡内他村の「千里山」への入合阻止を図り、最終的には一応の成功を見ているようだ。
ところが、地元桜井谷では、これ以降も近辺の山をめぐる争論に伴っていくつかの文書が残されているが、それらの文書には「千里山」の名称が見当たらない。1575(天正3)年から1624(寛永元)年までの、山年貢の推移を記した文書(中川衛文書:豊中市史資料編三)には、
- 慶長二年ニ新免村原田郷と出入御座候
- 慶長七年三月廿八日ニ新免村原田郷ノ者山へ入、柴松木等を切取申候を、片桐市正様御断申上、左之通無相違
などと、慶長の山論に言及したと思われる箇所がある。本文書は「桜井山御年貢初り増米」と頭書されており、桜井谷の東西の山を含んでいるかも知れないが、いずれにせよ「千里山」という名称は使われていない。
更に、1669(寛文9)年9月21日付で桜井谷六ヶ村の庄屋・年寄連名で奉行に提出された「桜井村ヨリ竹谷山公事之返答書」(豊中市史資料編三)では、文書名にもある通り「竹谷山」という名称が現れる。この文書では、問題になっている場所は明確だが、地名の解釈の相違そのものが論争の手段にされている節もあり、事態が複雑になっている。まず、問題の「竹谷」あるいは「竹谷山」について、
- ・・・熊野田村より被指上候御目安ニ、当村より五六町北川上ニ竹谷と申山之谷・・・
- ・・・以之外成偽りニ而、此竹谷と申山は惣名ニ而、
- 熊野田領之竹谷山と桜井領之竹谷山との境目ハ、山田之新田村桜井村熊野田村三ツあひを三階か峯と申候、此三階か嶺ヨリ谷川を切、未申ニ当り、われたか辻と申所、桜井領熊野田領之堺目にて御座候、
- 惣竹谷と申山ハ、南ハ熊野田領之池田道より迄、南者熊野田領念仏山を切、北者桜井領内かなつる瀬西桜井領之内蒐原岡を切、竹谷と申惣名ニ而、其内ニ字数多御座候、
- 熊野田ヨリ被申上候ハ、東ハ鷹が巣と申所より岡を切、西ハ横峯南四辻中道を堺目抔と押領被申掛、
としている。兎川の谷に関して、熊野田側が「竹谷」と呼んで自村分の検地帳に記載されており、その北部まで自領と主張したのに対し、桜井側は「竹谷」は島熊山も仏念寺山も含む広い範囲の山の総称であって、「竹谷山」にも「竹谷」にも、桜井領と熊野田領の両方が含まれるとする。同様の地名解釈の相違は、天竺川についても展開されていて、熊野田側が西側支流を指して「天竺川」と呼んだらしいことに反発し、
- 熊野田村より被申上候者・・・桜井村之者・・・天竺川へ土砂を流し、川下之在々迄迷惑致させ候と被申上、
- 以之外成難題、何ヨリ以迷惑ニ奉存候、
- 天竺川と申者熊野田村、東より南よりへ流申川ニて御座候、
熊野田村の中を横切って流れる川に、自分達が踏み込んで土砂を流すわけがないではないかと主張している。
こうした争論の中で、もはや「千里山」は問題ではなく、桜井谷六ヶ村は、戦略的に「竹谷山」を「惣名」として前面に押し出している。「惣名」を含む「惣名」などが出てくると事態が紛れるので、彼等にとっては、むしろ「千里山」などという「惣名」は邪魔なだけだったろう。
更に時代が下ると、今度は固有名詞的な「惣名」が登場しなくなる。1759(宝暦9)年2月16日付桜井谷六ヶ村庄屋年寄連名の小堀数馬役所宛文書(中川衛文書:豊中市史資料編三)では、村の周辺の山を「小堀数馬様御支配所御小物成場所山林」と総称し、
- ・・・東西之山絵図等持参仕、
- ・・・右東西山林之内字玉坂山照月山、
- ・・・六ヶ村ニ山と申所外ニ無御座候ニ付、則東西之山林之内ニ而ハ、勝手次第ニ伐被申候儀ニ御座候、
- ・・・天正年中ヨリ御年貢上納仕来、慶長年中ニ両度迄原田郷新免郷より山林押領可致といろいろ申懸ケ、其節片桐市正様へ被為召出、桜井六ヶ村之差配ニ相極リ、
- 右六ヶ村立合之山林字東山四拾壱町六反六畝弐拾歩、字西山拾八町歩弐ヶ所、
と、固有名詞色の薄い字名を用いて呼んでいる。この頃の主たる関心事は、小物成場の増石・請負問題なので、対象地域を過不足なく表現するのには、こうした表現が適切だという意識があったのだろう。
結局のところ、「千里山」について、現存する古文書類から直接わかることは、
- 慶長年間、豊臣政権の奉行サイドからは、桜井谷・熊野田の周辺の何がしかの範囲の山が「千里山」と呼ばれていた。これが、地名としての「千里山」の初出であるが、その指している範囲は明確ではない。また、読みについては明示されていない。
- 上記の山論の当事者であった桜井谷・熊野田の地元サイドで、村の利害にかかわる場面で「千里山」の称が用いられた形跡はない。
といった程度だ(桜井谷を中心とした水論関係の文書に現れる「千里川」については、後で触れる)。
それでは、桜井谷から「千里山」の名は姿を消してしまったのかと言うと、そうではない。桜井谷六ヶ村中で最も北に位置する野畑村には、近世から続く小字名として千里山・千里山ノ谷があり(宅地化されて「緑丘」となる)、少なくとも1960年代までは、千里山ノ谷に千里山池(現緑丘五丁目)が存在していた。また、桜井谷村の松井重太郎が1931年以降書き続けた大部の稿本「桜井谷郷土史」には、近代の桜井谷に伝わっていた「千里山」観がよく表現されている。
- 東山の記述を『千里山(東山)』と題する。(第二章第一節)
- 桜井谷の東、郡境の山が「千里山」である。(第二章第一節(一))
- 「千里山脈」の名は「千里山」に由来する。(第二章第一節(一))
- 千里山には三峰が連なり、北から番小屋山・三蓋峰・島熊山と呼び、古くは三峰を総称して三蓋峰と称した。(第二章第一節(一))
- 番小屋山は、千里山脈の最高峰である。(第二章第一節(一))
- 「東山」は、桜井谷領の「千里山」の総称である。(第二章第一節(六))
- 三分岐する「千里山ノ谷」の南側支谷を登り詰めた所が、番小屋山である。(第二章第一節(六))
- 刀根山・待兼山の並びの記述を『千里山(西山)』と題する。(第二章第二節)
- 千里山の総名である「東山」に対して、待兼山等北が「西山」、西は「刀根山」である。(第二章第二節)
これらの記述中、地誌の千里山観を思わせる『千里山(西山)』のような揺れもあり、郡界の東に広がる千里丘陵本体をどう見ていたかが不明であることもあって、すっきりしない点は残る。しかし、少なくとも、この筆者が「千里山」と言うときにまずイメージしたのが、桜井谷の東に連なる丘陵地の稜線中、桜井谷領の番小屋山・三蓋峰と熊野田領の島熊山の並びであったことには、疑問の余地がない。「千里山ノ谷」も、その「千里山」の最高峰である番小屋山に向かう谷である。また、この筆者は、明らかに陸軍測量部の(おそらくは1921年実測の版あたりの)地形図を見ているが、三蓋峰からわずか1km程東北に133.8m地点が明記されているにもかかわらず、131.7mの番小屋山を、わざわざ標高を明記した上で「千里山脈中ノ最高峰」としていることから、彼にとっての「千里山脈」もまた郡境の稜線の連なりに限ったものであったことが窺える。
もしも、この「千里山」が、近世から近代を通じての桜井谷の千里山観を継承したものであり、慶長の「千里山」につながるものであるならば、慶長の「千里山」は、ほぼ桜井谷の東山に相当し、それに南方熊野田領への若干の延長を加えた範囲を指していたという推測が、一層根拠のあるものとなってくる。
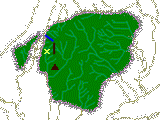 | | 桜井谷の千里山
┃:東山三蓋峰(番小屋山-三蓋峰-島熊山)
\:千里山ノ谷
×:桜井谷六ヶ村と熊野田村の争論地
▲:仏念寺山(竹谷山南限「念仏山」か?) |
この章の最初に、慶長文書を「千里山」の初出と紹介した。それは、明確に「千里山」が出てくる文書の最古のものという意味では嘘ではない。ところが、それよりはるか以前の1343(北朝康永2)年2月の垂水荘預所代助正陳状案(東寺百合文書な一−一〇)には、次のようなくだりがある(吹田市史第五巻による)。
- ・・・雖然同三季八月日大洪水之時、十尋河水出、円隆寺前提(堤)切候畢、仍莫太(大)之公田浜成候、・・・件十尋河云者千重(里)山之山河候也、而洪水之時、山崩砂流下、若于公田荒浜成候、・・・
これは、垂水の四条一里〜三里(現江坂の大部分)五条二里(現小曽根の一部)を垂水荘として支配していた東寺に宛てて、現地を管理する公文代の助正が提出した訴状の一節で、1336(建武3)年8月に「十尋河」が円隆寺付近で決壊し、田地に被害が出たことを述べている。同じ1343年に作成された垂水荘内検取帳(東寺百合文書わ五下−六:吹田市史第五巻による)を見ると「円隆寺堂敷宮敷四反半」は、四条一里の廿七坪丁にあることがわかり、決壊した位置が現在の高川の左岸に当たることが推測できる。「十尋河」が現高川あるいはその前身であることは、ほぼ間違いないだろう。さてこの陳状の中では、「十尋河」は「千重山」の山川であると言っている。この「千重山」が、千里丘陵あるいはその南西部を指していることは明白だ。吹田市史の編者が註しているように「千重山」は「千里山」の誤記なのだろうか。それとも「せんぢう山」という呼称が、この時代の垂水にあったのだろうか。前者なら「千里山」の初出年代が大幅に遡ると共に、「千里山」が早い時期から千里丘陵西南部をも含んだ称であったことになる。後者なら、もっと別の関心が湧いてくる。それは、もっと後の章を読めば、気付いてもらえると思う。
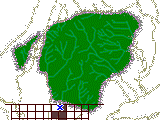 | | 1336(建武3)年の洪水
■:東寺領垂水荘
(四条一〜三里・五条二里)
×:「十尋川」決壊地点(推定) |
←前|↑表紙|→次