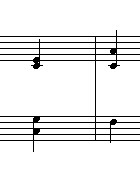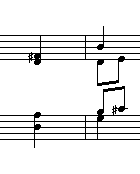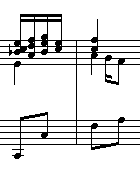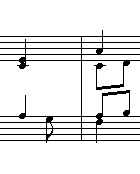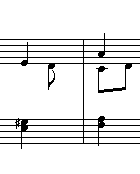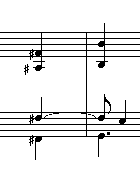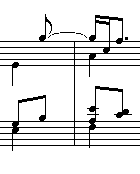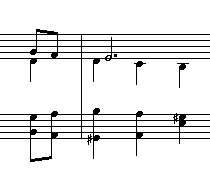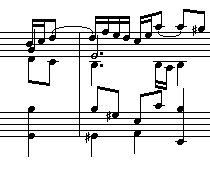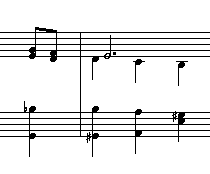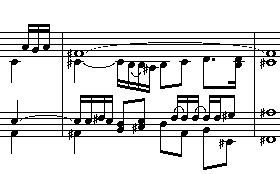目次
"O Haupt voll Blut und Wunden" あるいは "Herzlich tut mich verlangen"
H.L.ハスラー作の恋愛歌(1601)として流布した曲が、死後の平安を想うコラール"Herzlich tut mich verlangen"(1613)となり、やがてドイツ全土で三十年間続いた宗教戦争の後、P.ゲルハルトの訳詩を得てキリスト受難のコラール"O Haupt voll Blut und Wunden"(1656)へと変容していった話は、マタイ受難曲に関連して、あちこちで紹介されている。バッハの時代、18世紀前半には、これらのコラールは、既にドイツ・プロテスタントの信徒には、なじみの深い歌となっていた。
しかし、すべてが「昔ながら」だったわけではない。百年あまりの間に、コラールも徐々に変化が生じていた。一つは、リズムの変化だ。16世紀末の段階では、コラールは、ルター以来の、長短組合わさった、生き生きしたリズムで歌われるのが普通だったろうと言われている。ところが、18世紀初頭の楽譜では、現在我々がコラールの一般形として知っている、各音符を原則として同じ長さで歌う、平板なリズムになっていた。最近、日本で発行された「賛美歌21」には、従来形のもの(賛美歌136番として知られている形)とともに、ハスラーに遡る、三拍子リズムに復した形が掲載されている。
もう一つは、旋法・調の変化だ。中世的な教会旋法は、次第に近代的な長調・短調に駆逐されていった。バッハの時代、既に「今ふう」の音楽は、長調・短調であって、教会旋法を採り入れる時は、意識的に、クラシックな、あるいは宗教的・神秘的な雰囲気を演出する場合(もちろんバッハにその例は多い)に限られつつあった。バッハによるコラール編曲は膨大なものだが、彼はこれら「伝統的な歌」に、時と場合に応じて、様々な色合いを与えた。はっきり長調・短調の和声付けをされることも多いが、時には教会旋法風の和声付けをされることもあり、一つのコラール旋律に、異なる調性の和声を付けた例も珍しくない。
さて、このコラール"O Haupt voll Blut und Wunden"/"Herzlich tut mich verlangen"の旋律は、要するに「ミ」ではじまって「ミ」で終わる。この「ミ」を、音階の3番目の音と捉えれば長調になるし、5番目の音とすれば短調になる。そして、もっと素直に「ミ」を本来の終止音だとし、旋律が頻繁に上の「ド」を使うから、この「ド」を支配音とすると、教会旋法で言うフリギア調にあたる。これらの違いは、端的には、最初の和音が「ドミソ」なのか「ラドミ」なのか「ミソシ」(「ソ」が半音上がる場合とそうでない場合がある)なのかということに現れる。おもしろいことに、二番目の和音は、どの例でも基本的に「ファラド」で変わらないので、このコラールの冒頭の印象を決定づけるのは、ひとえに最初の和音が何か、ということにかかっているわけだ。
| 長調 | 同左 | 長調(七度を伴う) | 短調 |
|---|
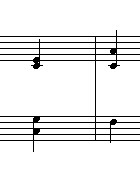 |
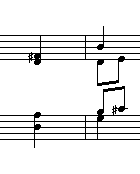 |
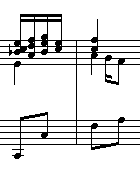 |
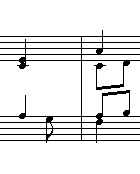 |
|
賛美歌136番(マタイ受難曲「私を見て下さい、守り手よ」「私はあなたのもとに留まる」「あなたの道を委ねよ」を移調したものも同じ)
|
クリスマスオラトリオ「報いられる時が来た」
|
カンタータ161「おいで甘美な死の時よ」
|
マタイ受難曲「いつか私が世を去るときに」(同「おお頭は血と傷にまみれ」を移調したものも同じ)
|
フリギア調
(長三和音) | 同左 | フリギア調
(短三和音) |
|---|
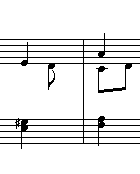 |
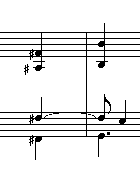 |
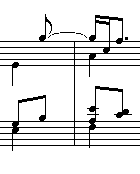 |
|
クリスマスオラトリオ「どのようにあなたを迎えよう」
|
オルガンコラール「私の心からの願い」
|
カンタータ161「この身は地中で虫の餌食になっても」
|
はじまりの和音に比べると、最後の和音は、種類が少ない。要は「ドミソ」か「ミソ#シ」しかない。長調・短調ではじまった場合は、前者、つまり長調で終止し、フリギア調ではじまった場合は、後者になる。ただし、マタイ受難曲「いつか私が世を去るときに」は、短調ではじまり、最後は「ミソ#シ」に落ちる。さて、前者の終止形は、属和音から主和音に入る素直なものだが、後者の終止は、長三和音「ソシレ」から入るものと、短三和音「ソシbレ」から入るものとがあり、いずれも、一発では終止感がないためか、きまって七度の係留を伴い、いったん「ラドミ」に振れてからもう一度「ミソ#シ」に落ちて終わる。
特殊形や折衷的な形はあるものの、このコラール旋律への和声付けは、当世風の長音階和声と、中世的なフリギア調風とに大別されると言える。バッハの当時にあっても、この両者は、それぞれ「新しい感覚」と「古い感覚」を想起させるものだっただろう。
大雑把に見ると、受難コラール"O Haupt voll Blut und Wunden"としての側面が強く出ている場合には、バッハは長音階的・全音階的和声で力強く歌わせ、"Herzlich tut mich verlangen"系のイメージを前に出す場合には、フリギア調を基調にしつつ、半音階的な変化も織り込んで、内省的な音楽に仕立てているように思える。受難コラールの一節に属しながら、歌詞内容では"Herzlich tut mich verlangen"と強い親近性を持つ「いつか私が世を去るときに」は、イ短調で開始されてフリギア調風に結ばれる。歌詞に相応して、音楽もまた両方の系列の統合を意図しているかのようだ。
目次